社会人として仕事に追われながらも自己成長のために勉強時間を確保したい――そんな20代男性は多いでしょう。
しかし、無理をすれば睡眠不足で仕事にも支障が出かねません。
本記事では社会人の睡眠時間と勉強時間の両立に焦点を当て、睡眠の重要性や効率的な時間管理術、平日・休日のバランスの取り方などを解説します。
仕事で疲れていても眠気に負けず勉強を続けるコツや、実際に成功している人のルーティン例も紹介し、無理なく両立するためのヒントを提供していますので、勉強を続けられないと悩んでいる方はぜひご覧になってください。
社会人の睡眠時間と勉強時間の両立が難しい理由
社会人になるとどうしても仕事で疲労困憊し、勉強時間を確保するのが難しいものです。
特に20代の若手男性は「仕事後に勉強しよう」と意気込んでも、残業や通勤でヘトヘトになり、つい勉強する前に眠くなってしまうことも多いでしょう。
実際、夜に勉強しようとしても仕事終わりの疲労や誘惑が障壁になります。
例えば、19時過ぎに退勤して食事や入浴を済ませ21時から勉強を始めても、翌朝7時起床なら1時には寝ないと睡眠6時間を切ってしまいます。
このわずか4時間の勉強時間でさえ、満腹後の眠気やSNS・動画配信など夜の誘惑に邪魔され、集中できずに時間だけが過ぎてしまうことも少なくありません 。
結果として、勉強しようとしても眠気と戦う羽目になり、「疲れて勉強どころではない…」と感じてしまうのです。
仕事で日中に全力を尽くせば、夜には誰しも疲れが出ます。
ついソファでうたた寝してしまったり、会議中にウトウトしそうになった経験はないでしょうか。
社会人男性であれば、仕事の疲れから平日の勉強時間を捻出すること自体が大きな課題だと共感できるはずです。
このように、「疲れ」と「時間不足」が両立を阻む大きな理由となっています。
睡眠不足が勉強効率に与える影響
両立のために真っ先に考えがちなのが「睡眠時間を削って勉強時間を増やす」という方法です。
しかし、これは逆効果になりかねません。睡眠は学習効率に直結する重要な要素だからです。
実際に、受験指導の専門家も「睡眠不足になると、集中力や記憶力が低下し、学習の効率が悪くなる」うえに「ストレスが増え、体調不良の原因にもなります」と指摘しています 。
社会人の勉強でも同様で、睡眠を削ってしまうと仕事中のパフォーマンス低下や勉強内容の定着不良を招いてしまいます。
また、人間の脳は睡眠中に記憶を整理・定着させると言われています。
つまり、せっかく勉強しても十分な睡眠が取れなければ記憶が定着しにくいのです。
ある社会人向けの学習記事でも「その日の勉強内容を定着させるためには6時間以上の睡眠が必要です。ほどほどにして、しっかり寝るようにしましょう」と注意喚起しています。
勉強時間を1時間増やすために睡眠を1時間削ったとしても、寝不足で翌日の仕事効率が落ちたり勉強した内容を忘れてしまっては本末転倒です。
睡眠の質もまた重要です。
長さだけでなく質を高めることで、短い睡眠でも深く休息し疲労回復を図れます。
就寝前にスマホやテレビを見続けない、寝る前にリラックスする習慣を持つなど、睡眠の質向上も勉強との両立には欠かせません。
しっかり眠って脳と身体を回復させることが、結果的に勉強効率アップや集中力維持につながるのです。
効率的な時間管理術で勉強時間を確保する
仕事と勉強を両立するためには、限られた時間を効率よく使う時間管理術が不可欠です。
1日は24時間しかない中で、睡眠と仕事の時間はある程度固定されています。
その残り時間をどう工夫して捻出するかが勝負です。
「勉強する時間がない」と感じている人も、日々の生活を見直せば意外とスキマ時間が見つかるものです。
以下に、社会人が無理なく勉強時間を生み出すための具体的な時間管理術を紹介します。
朝の時間を活用して勉強する
まず注目したいのが出勤前の朝時間です。
多くのビジネスパーソンが夜型で勉強しようとしますが、実は朝型に切り替えるのが両立成功のカギになります。
頭が一番すっきりして集中できる朝に勉強を持ってくることで、夜に疲れて勉強が進まない状況を避けられます。
実際、とある学習法の記事でも「勉強スタイルには朝型と夜型がありますが、朝の勉強を重視することをすすめます。
早起きして学習時間のなるべく多くを朝のうちに終えることが効率的です」と述べられています。
出勤前の1時間でも、フレッシュな頭で問題集を解いたり暗記物に取り組めば夜にだらだら取り組むより効果的でしょう。
朝早く起きるのは慣れないうちは大変ですが、少しずつ習慣化すれば体も順応してきます。
コツとしては「勉強のために早起きしなきゃ」と意気込むより、「美味しいモーニングを食べに行く」「満員電車を避けて早めに出勤する」など他の目的で早起きを試みることです 。
早起きそのもののハードルを下げる工夫をすると、結果的に朝の時間が確保しやすくなります。
朝型生活にシフトできれば、夜は早めに寝て睡眠時間を確保しつつ、勉強時間を捻出できる好循環が生まれるでしょう。
通勤や休憩などスキマ時間の活用
社会人ならではの通勤時間や仕事の合間の休憩時間も、貴重な勉強チャンスです。
片道30分~1時間の通勤電車・バスの中で、ただスマホでSNSを見たり音楽を聞いたりしていませんか?
その時間をぜひ勉強に充ててみましょう。
テキストや単語帳を開くのが難しい満員電車なら、スマホで電子書籍や学習アプリを使ったり、語学や資格試験向けの音声教材・講義動画を再生するのも効果的です 。
耳から情報を入れるオーディオラーニングは、歩いている時や車通勤でも活用できます。
また、昼休みやちょっとした休憩時間に5〜15分程度でもミニ勉強セッションを入れると積み重なれば大きな差になります。
例えば昼食後にコーヒーを飲みながらニュース記事を英語で読む、休憩中に資格試験の用語集を眺めるなどです。
こうしたスキマ時間の活用は、「まとまった勉強時間が取れない…」という焦りを和らげ、勉強の習慣化にもつながります。
夜の過ごし方を見直す
仕事が終わった後の夜の時間も、見直し次第では勉強時間を生み出せます。
ただし、夜は一日の疲れがピークに達しているため、無理は禁物です。
ポイントは、だらだら過ごしてしまっている時間を減らすこと。
たとえば夕食後から寝る前まで、ついテレビや動画サイトを何となく見ていないでしょうか。
そのうち30分でも1時間でも勉強に充てれば貴重な学習時間になります。
就寝前の時間帯は記憶の定着がしやすいとも言われますので、英単語や用語の暗記に充てるのもおすすめです 。
ただし、夜更かしのしすぎには注意が必要です。
先述の通り睡眠不足は効率を下げるため、夜に勉強する場合でも「○時まで」と区切りをつけましょう。
実際に「夜遅くまで勉強しすぎないことです。
その日の勉強内容を定着させるためには6時間以上の睡眠が必要です」との指摘もあります。
勉強に熱中するあまり深夜まで起きていては翌日に響きます。
メリハリをつけて適度なところで切り上げ、しっかり寝ることが長い目で見て両立を成功させるコツです。
休日の勉強計画とリフレッシュ
平日になかなか勉強時間を取れない分、休日はまとめて勉強するチャンスです。
しかし、休日だからといって一日中勉強漬けにするのも現実的ではありません。
ポイントは無理のない計画を立てることです。
ある社会人向け記事でも「休日にやるぞ!と決めたことが消化できず、残念な気持ちになった経験はありませんか?」と問いかけ、最初から詰め込みすぎないよう注意しています。
休日は本来休息の日でもあるので、勉強とリラックス双方の時間をバランスよく確保しましょう。
具体的には、休日の午前中を勉強に充てて午後は自由時間にする、といったメリハリをつける方法がおすすめです。
午前中は頭も冴えているので集中しやすく、4時間程度まとまった勉強ができます。
午後は友人との予定や趣味の時間に使ってリフレッシュすれば、精神的にも満たされます。
仮に土日それぞれ午前に4時間ずつ勉強すれば週8時間を確保できますし、平日が忙しくてもトータルの勉強時間を底上げできます。
大切なのは、休日も生活リズムを崩しすぎないことです。
平日とのリズム差が大きいと月曜がつらくなり、平日の勉強習慣も乱れてしまいます。
平日より少し長めに寝て疲労回復しつつ、朝はいつもより遅めでも決まった時間に起きるようにすると良いでしょう。
そうすれば午前中の貴重な時間を勉強に使い、午後は余裕を持って過ごすというサイクルが無理なく続けられます。
20代社会人の勉強時間確保の成功例
実際に仕事と勉強を見事に両立している20代社会人の例を見てみましょう。
新卒2年目・20代のある男性(税理士試験受験生)は、平日と休日を上手に使って週20時間以上の勉強時間を確保しています。
彼のルーティンはシンプルかつ実行可能な内容です。
- 平日: 毎朝約1.5時間の朝勉強+仕事後に1時間の勉強を日課とし、平日5日で合計約12.5時間の学習時間を確保。
- 休日: 午前中に4時間、午後に1時間程度の勉強を行い、土日の合計で約10時間を勉強に充てる。
このように平日と休日を組み合わせることで、1週間で合計約22.5時間(予備を見て20時間)の勉強時間を捻出しているのです。
ポイントは、朝型の生活リズムと毎日の継続にあります。
彼は朝5時45分に起床して6時から7時30分まで勉強する習慣を身につけており、冬の暗い時期でも続けられるようになったといいます 。
起きた直後は眠気があるため、声に出して理論科目を暗記しながら体を動かし、徐々に脳を目覚めさせる工夫もしているそうです。
こうして朝にエンジンをかけ、夜は帰宅後に1時間だけ問題演習などに取り組み就寝しています 。
この成功例から学べるのは、毎日の少しずつの積み重ねとメリハリある計画です。
朝早起きして勉強し、夜更かしはしないことで睡眠時間も確保しています。
休日も午前中に集中して勉強する代わりに午後は休むというバランスで、無理なく継続できています。
結果として「平日2.5時間×5日+休日5時間×2日=約20時間/週」という理想的な両立を実現できているのです。
もちろん個人差はありますが、「朝型にシフト」「短時間でも毎日続ける」「休日は計画的に使う」といったポイントは、多くの社会人に応用できるでしょう。
まずは真似できる部分から取り入れて、自分なりの両立ルーティンを作ってみてください。
まとめ:睡眠も勉強も味方につけて無理なく両立しよう
仕事で疲れていても工夫次第で睡眠時間と勉強時間の両立は可能です。
大切なのは、「睡眠不足になれば勉強も仕事も効率が落ちる」ことを理解し、無理せず質の高い睡眠を確保すること。
【社会人の睡眠時間と勉強時間の両立】には早朝や通勤など隙間の時間管理術、そして習慣化による継続力がカギとなります。
まずはできる範囲で朝型の勉強習慣やスキマ時間活用を始めてみましょう。
十分に睡眠をとりつつ勉強を続けられれば、心身の健康と自己成長の両方を手に入れられるはずです。
今日からぜひ小さな一歩を踏み出して、仕事も勉強も充実した毎日を目指してください。




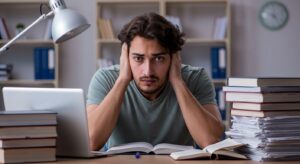

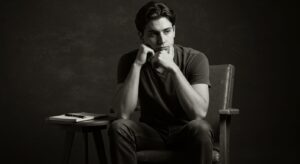




コメント